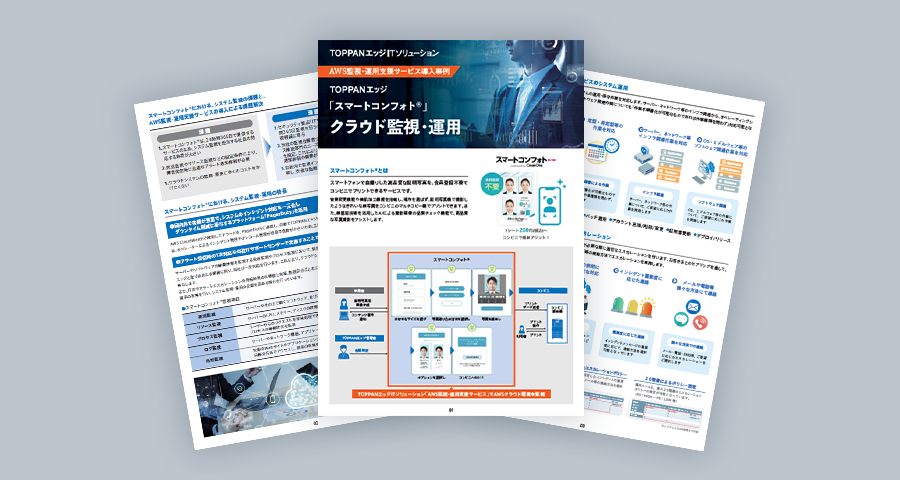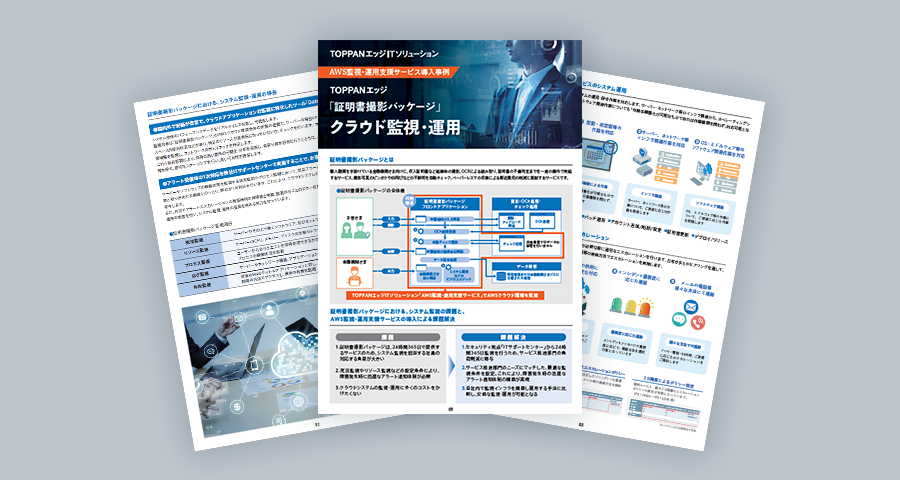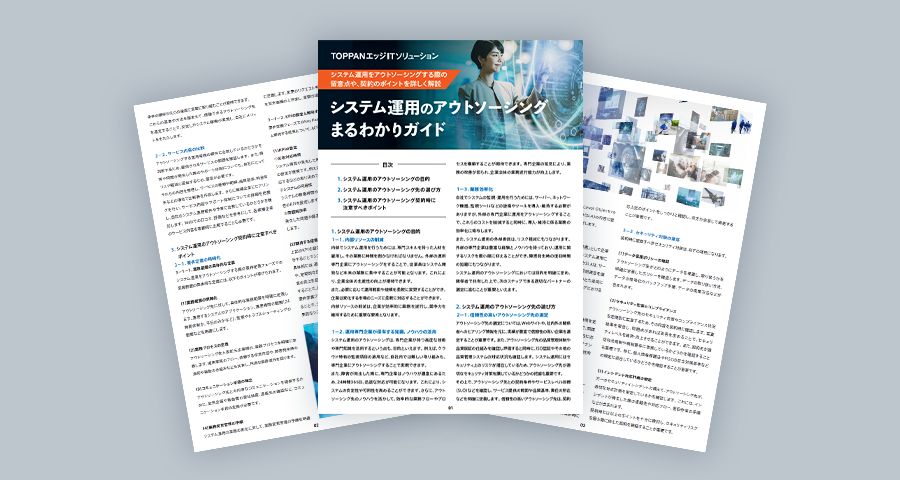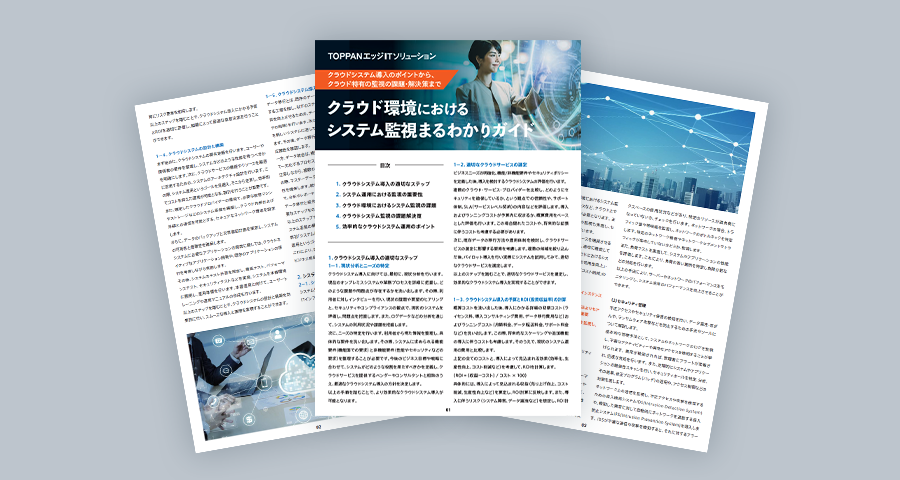24/365運用とは? システムの安定稼働に向けた実施内容や課題解決策
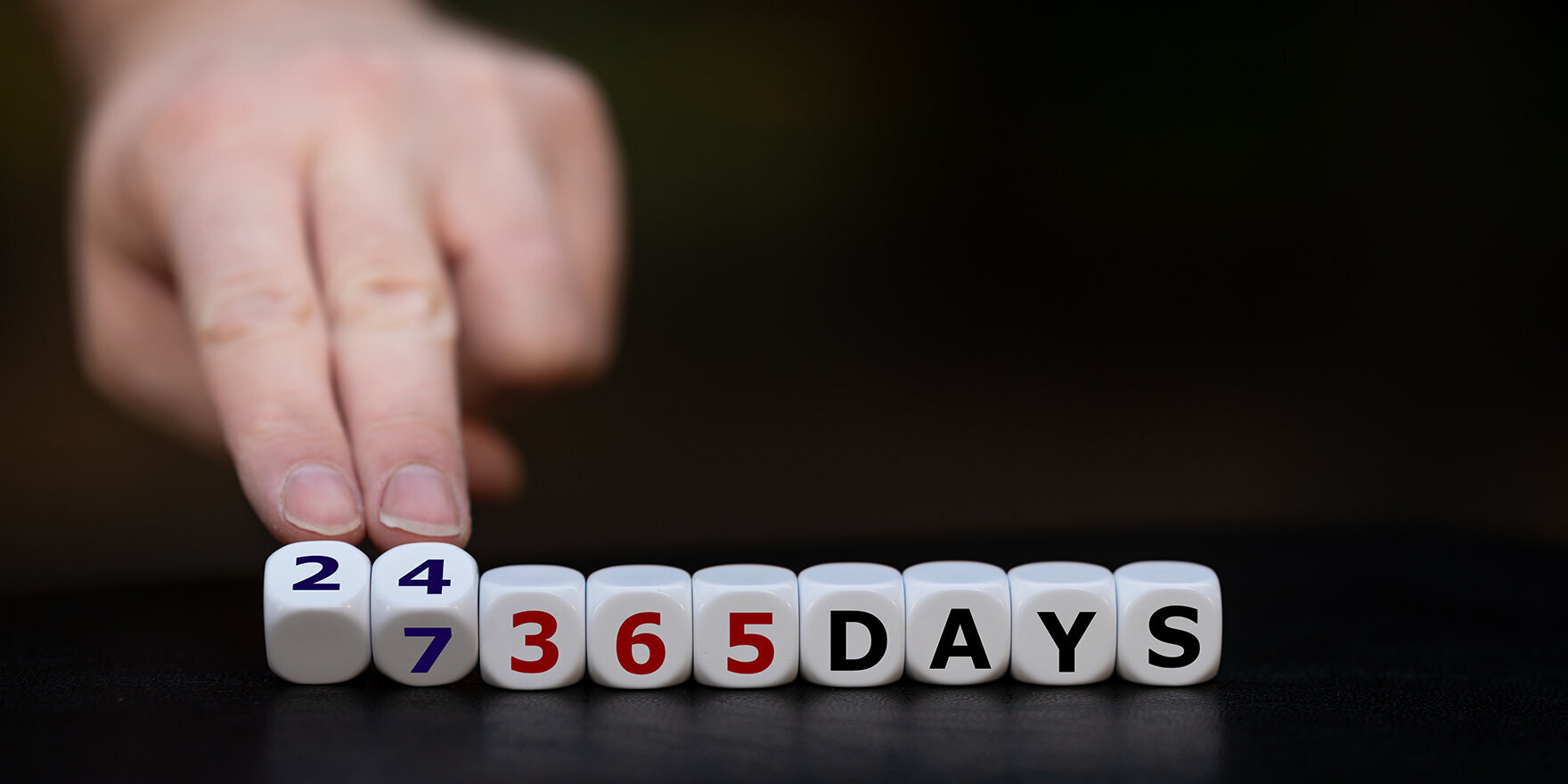
近年、企業が提供するサービスやシステムが常に「止まらない」ことへの要求が高まっています。
インターネットでのサービス提供が当たり前となり、グローバルに利用者がいる場合、時間や国境を問わずにサービスを稼働させ続ける「24時間365日(以下、24/365)」運用は不可欠です。
本コラムでは、24/365運用とは何か、その実現に必要な取り組みや課題、そして課題解決のポイントを解説します。
目次
閉じる
01.24/365とは?
「24/365」とは、1日24時間、年間365日を通してシステムを稼働させることを指します。たとえばECサイトや金融機関のオンラインサービス、クラウドアプリケーションなどは、世界中のユーザーがいつでもアクセスできるよう、止まらないシステムを目指すことが求められます。もし障害やメンテナンスのために長時間サービスが停止すると、利用者の不満や信頼低下、売上の損失など、事業継続における大きなリスクにつながります。
24/365の運用を維持するためには、単にシステムが「動いている」状態を保つだけではなく、将来的な拡張性やセキュリティ面、障害発生時の復旧力など、あらゆる観点で高いクオリティを求められます。とりわけ障害検知の迅速化や原因の切り分け、対処までのスピードは事業継続の鍵となります。このような運用を整備することは、多くの組織にとって避けては通れないテーマとなっています。

02.24/365のシステム安定稼働を実現するためにやるべきこと
24/365でシステムを止めることなく稼働させるためには、日常的な運用体制の整備だけでなく、障害やセキュリティリスクを未然に防ぐ仕組みづくりが不可欠です。
ここでは、そのために取り組むべき主要な事項を紹介します。
システム監視
24/365運用の土台となるのが、システム監視の仕組みです。サーバーのCPUやメモリ使用率、ディスク容量、ネットワークトラフィックなど、稼働状態やパフォーマンスに影響を与える要素を常時モニタリングし、異常値が見られたら即座にアラートを上げます。また、アプリケーションの応答速度などを監視することで、処理遅延やエラーログの蓄積などもリアルタイムで把握可能です。
監視には、ZabbixやDatadogなどのツールを利用するケースが多く、情報収集と可視化を自動化する仕組みが一般的です。検知後の初動対応をどうするか、誰が担当するか、夜間や休日のアラート対応をどのように切り分けるかなど、運用ルールまで含めた設計がポイントになります。
セキュリティ対応・強化
24/365運用では、一瞬でもシステムが停止すれば利用者に大きな影響を与えるため、サイバー攻撃や情報漏えい対策は最優先課題のひとつです。ファイアウォールや侵入検知システム(IDS/IPS)の導入だけではなく、OSやミドルウェアを常に最新バージョンに保つ、脆弱性情報を収集して早めにパッチを当てる、といった基本的な運用体制の確立が重要になります。
定期的なパフォーマンス評価と最適化
24/365運用を維持するには、常に十分なリソースを確保し、ピークアクセスにも耐えられる体制を整える必要があります。具体的には、CPUやメモリ、ディスクI/O、ネットワーク帯域などの利用状況をモニタリングし、ボトルネックとなりうる要素を早期に洗い出すことが重要です。
また、こうしたパフォーマンス評価は一度行えば終わりというものではなく、ビジネス規模の拡大やサービス仕様の変更にあわせ、定期的に見直すことが求められます。性能計測の結果に基づいてリソースの割り当てやシステム構成を随時最適化し、不要なコストをかけずに安定稼働を実現していくことが鍵となります。

03.24/365運用を自社で行う場合の課題
高度な運用体制を自社内だけで整えることは、決して簡単ではありません。ここからは、24/365運用を内製化する場合に直面しがちな課題を見ていきましょう。
対応可能な人的リソース
24/365のシステム監視・運用を行うには、夜間や休日を含めて常時監視できる人員が必要です。シフト制を導入したり、オンコール体制でアラート時に担当者を呼び出す仕組みを作るなど、人員配置の工夫が求められます。さらに、深夜帯や休日の障害は発見が遅れるだけでなく、担当者が確保できない場合、復旧に時間がかかり大きなリスクが発生することもあります。
少人数のIT部門で日中の通常業務に加えて夜間対応も担うと、メンバーの疲弊や離職率の上昇を招きやすく、長期的には組織運営やサービス品質に大きく影響を与えるでしょう。
ノウハウ蓄積~教育~対応にかかる人件費
監視や運用の仕組みを整備するためには、高度なITスキルを持つ人材を採用したり、社内で継続的に教育を行う必要があります。サーバー、ネットワーク、セキュリティなど複数の専門領域が必要となるため、適切な人材が限られた場合は、特定のメンバーに作業が集中しがちです。
また、新たなシステムを導入するたびに運用マニュアルを更新し、教育を繰り返す作業は、想定外に大きなコストと手間を伴います。
運用フェーズで発生する人件費やノウハウ蓄積のための時間などで、トータルコストが膨れ上がってしまうケースが多々あります。
運用ツール・設備への投資負担
24/365運用を自社で行う上で、大きな障壁となるのが監視システムや運用管理ツールの導入コストです。
高機能なソリューションほど、ライセンス費用や保守サポート料がかさみやすく、ソフトウェアやハードウェアの更新サイクルに合わせて追加予算も必要となります。さらにIT技術の進化ペースが速い昨今では、常に最新状態を維持しなければリスクが高まります。結果として、内製化を進めるほど設備投資が増大しやすい点は見過ごせない課題といえるでしょう。

04.24/365運用を改善するポイント
前述の課題を乗り越え、24/365で安定稼働を実現するためには、「体制の整備」と「ノウハウの共有」が欠かせません。ここでは、具体的な改善策となるキーポイントをご紹介します。
体制構築と整備
まず、24/365の運用を支えるチーム体制をしっかりと設計しましょう。昼夜問わず監視を行う対策としては、「三交替制で常に数名を配置する」「オンコール担当をローテーションで回す」などの方法があります。一般的には、物理的な常駐チームを持つのが最も手厚いですが、人件費やシフト管理の面で負担が大きくなるため、SLA(サービスレベルアグリーメント)やSLO(サービスレベルオブジェクティブ)に合わせつつ自社に合った形を模索する必要があります。
あわせて、障害が発生した場合のエスカレーションフローや復旧手順を文書化し、チーム内で共有しておくことも重要です。誰がどのタイミングで作業を引き継ぐのか、不在時の代替はどうするのかなど、事前に取り決めておくことで混乱を防ぎ、復旧時間を短縮できます。
ノウハウを蓄積・共有する仕組みづくり
24/365運用では、個人の熟練度に頼りすぎると、特定の人への負担が集中しがちです。そうしたリスクを回避するためには、過去の障害事例や対応履歴をドキュメント化し、チーム全体で参照できるナレッジベースを整備することが有効です。クラウド型のプロジェクト管理ツールやWikiなどを活用し、社内の誰もが検索しやすい仕組みを作り、常に更新を怠らないようにしましょう。
また、新たなメンバーが加わった際にも、ナレッジベースを活用してスムーズに運用の実情を学べるため、教育コストの最適化や質の均一化に寄与します。ノウハウの共有は、24/365運用の"属人化"を防ぐうえで非常に重要な取り組みです。
運用プロセスの自動化・AIの活用
24/365運用の現場では、パッチ適用やログ監視といった定型作業に多くの工数が割かれがちです。こうした繰り返しのタスクは、スクリプトやRPAなどにより自動化することで、人手によるミスや作業の抜け漏れを削減するだけでなく、担当者がより高度な業務に専念することが可能になります。また、AIを用いて大量の監視ログやパフォーマンスデータを解析し、障害の予兆を早期に検知すれば、システム停止などのリスクの予防策を事前に打つことができるでしょう。
自動化・AI活用は、運用品質を高めながら人的リソースの負荷を軽減し、結果的に高水準な24/365運用を目指すうえで欠かせない要素となります。

05.24/365運用を外注するメリット
ここまで、自社で24/365運用を行う場合のポイントや課題を見てきましたが、それでも内製化が難しい企業も少なくありません。そのような場合、運用の専門家である外部サービスを活用する選択肢があります。以下では、外部委託で得られる利点を整理します。
コストを削減できる
24/365運用のために必要な人員を社内で雇用し続けることは、給与だけでなく研修費やシフト管理といったコストが伴います。さらに、監視ツールの導入費やライセンス料も少なくありません。外注サービスであれば、必要な範囲を契約すればよいため、初期投資を抑えやすく、運用コストを一定水準に安定化できます。リソースの増減に合わせてプランを調整できる点もメリットです。
本業に注力できる
自社のIT部門が24/365の運用管理に追われると、新しいIT戦略の立案や更なるDX推進といったコア業務に十分リソースを割けなくなります。アウトソーシングにより運用部分を任せれば、専門家が24時間体制で監視・障害対応を行うため、社内メンバーはビジネス価値を生む取り組みに集中しやすくなります。結果的にイノベーションを起こすチャンスも増大するでしょう。
障害発生時に迅速な対応ができる
監視・運用サービスを提供する企業は、多くの顧客システムを扱い、障害対応や脆弱性対策の知見を豊富に蓄積しています。昼夜を問わない体制や専門チームを既に擁しているケースが多く、障害を早期発見し、迅速な切り分け作業と復旧対応を行うことが可能です。特に、複雑なシステム構成を持つ企業にとっては、障害の原因特定や復旧のノウハウが豊富な外部パートナーの存在が大きな安心材料となります。

06.まとめ
24/365運用は、現代のビジネス環境においてほぼ必須ともいえる取り組みです。ユーザーがいつアクセスしても安定したサービスを提供し続けるためには、常時監視体制の整備やセキュリティ対策、障害対応の迅速化が欠かせません。一方、自社のみで体制を整えるとなると、高度なITスキルを持つ人材の採用・育成や、シフト管理の負担、ノウハウの属人化など多数のハードルが存在します。そこで、外部サービスを活用することで人的リソースの問題やコスト面を解消し、本業に専念できる体制を構築することも検討の余地が大いにあるでしょう。
当社では、お客さまのクラウドシステムを"24時間365日"体制で監視・運用する「AWS監視・運用支援サービス」をご用意しております。セキュリティ拠点「ITサポートセンター」の強固なセキュリティ対策のもと、経験豊富なエンジニアたちが常時システムを見守り、万が一異常を検知した場合には速やかにアラートを発報し、障害対応や原因究明を行います。
また、障害やセキュリティリスクを未然に防ぐための定期診断やレポート作成、最適化の提案など、幅広いサポートを包括的に実施し、"止まらないシステム"の実現を後押しします。
24/365運用の導入や体制構築にお悩みの際は、ぜひ当社のサービスをご活用ください。
AWS監視・運用支援サービスの特長
- ITサポートセンターによる監視体制
24時間365日体制で当社ITサポートセンターからシステム監視を行い、リアルタイムでの異常検知を行います。経験豊富なエンジニアやオペレーターが常駐し、障害発生時には迅速に対応することで、顧客のビジネスに最小限の影響で済むように支援します。監視拠点のITサポートセンターは、国内最高水準のセキュリティ体制を誇り、高い可用性でシステム監視・運用サービスを提供することができます。 - クラウドファーストに最適化した機能
クラウド環境でサービスを運用するお客様に最適な機能を備えており、クラウドの動的なリソース管理にも対応します。スケーラビリティを活かした監視を行い、リソースの自動拡張や縮小に合わせた負荷管理が可能です。また、現在オンプレでシステム運用を行っているお客さまに、クラウド基盤構築の支援も行います。クラウド基盤構築から監視・運用まで一貫したサポートで、お客さまのビジネス変革に貢献します。 - 継続的なサポートと改善提案
「AWS監視・運用支援サービス」では、単なる監視の提供だけでなく、継続的なサポートと改善提案も行います。これは、当社が50年のシステム運用実績で培ったノウハウと高い技術力により提供できるサービスと言えます。システムのパフォーマンス向上や新たなセキュリティ要件への対応など、定期的な評価に基づく提案を通じて、システムの健全性と運用効率の向上を支援します。企業ごとの運用要件に合わせた改善施策が提供されることで、長期的なIT戦略の実現をサポートします。