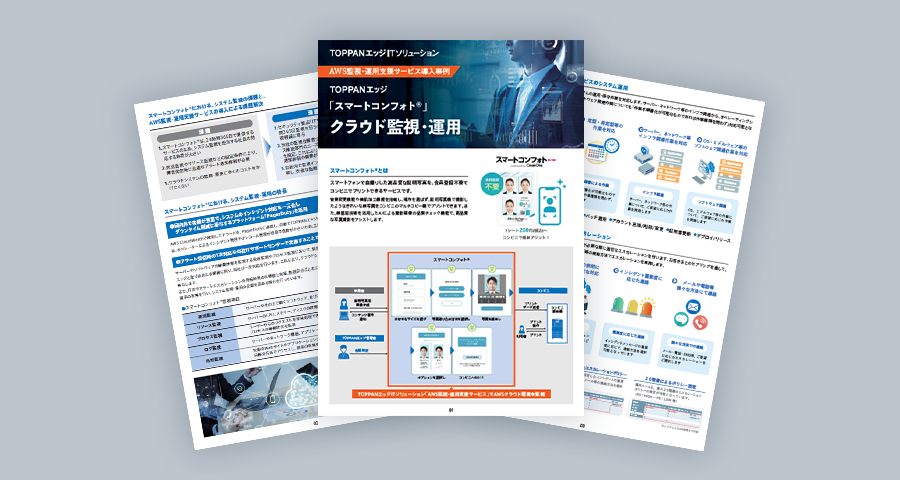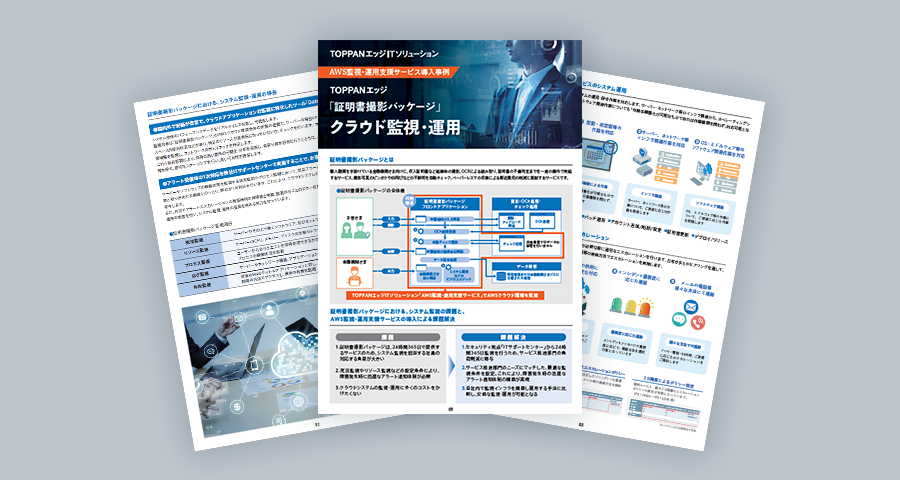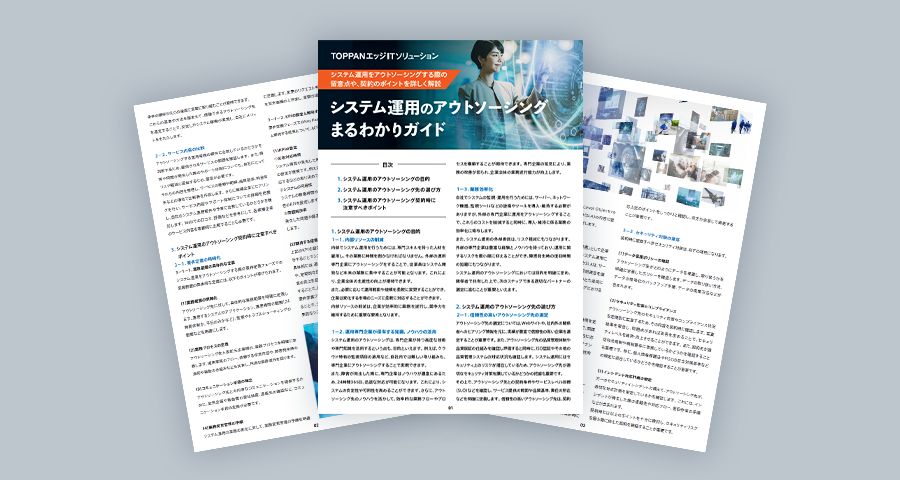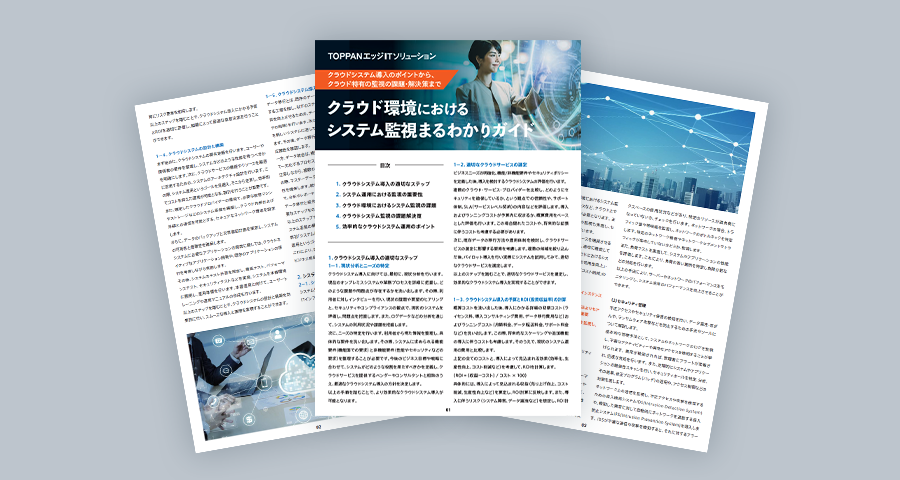クラウド構築とは? 概要から手順まで必要な基礎知識を解説

近年、クラウドサービスの活用が急速に広まり、企業のシステム運用や開発における選択肢として定着しています。本コラムでは、「クラウド構築」の基礎知識から、手順や注意点までをわかりやすく解説します。
目次
閉じる
01.クラウド構築とは?
クラウド構築の概要
クラウド構築とは、データやアプリケーションをインターネット経由で利用できるクラウド環境を設計・構築するプロセスを指します。従来のオンプレミス環境(自社内に設置されたサーバーやネットワーク設備)とは異なり、クラウドはリモートで管理可能なインフラやプラットフォームを活用します。
クラウド環境では、物理的な設備の設置や管理の負担が軽減されるだけでなく、柔軟性やスケーラビリティも向上します。これにより、企業はコストや運用負担を最適化しつつ、迅速なシステム展開を実現できます。
クラウドの種類
クラウドサービスには主に以下の種類があります。それぞれの特徴を理解し、用途に合わせて選択することが重要です。
IaaS(Infrastructure as a Service)
基本的なインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク)を提供します。ユーザーはこれらのリソースを自由にカスタマイズできるため、柔軟性が高いです。IaaSは、オンプレミス環境と同様の制御を求める企業に適しています。
例:Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform
PaaS(Platform as a Service)
アプリケーション開発用のプラットフォームを提供します。ユーザーはインフラ管理を気にせずに、アプリケーションの開発とデプロイに集中できます。PaaSは、開発プロセスの効率化と運用負担の軽減を目指す企業に適しています。
例:AWS:Elastic Beanstalk、Microsoft Azure:App Service、Google:Google Cloud Platform
SaaS(Software as a Service)
完成されたソフトウェアを提供します。ユーザーはインストールやメンテナンスを行う必要がなく、ソフトウェアの利用だけに専念できます。SaaSは、迅速にソフトウェアを導入し、運用コストを削減したい企業に適しています。
例:Microsoft365、Salesforce
DaaS(Desktop as a Service)
仮想デスクトップ環境を提供します。ユーザーはどこからでもデスクトップ環境にアクセスでき、セキュリティや管理が一元化されます。DaaSは、リモートワークを推進する企業や、セキュアなデスクトップ環境を提供したい企業に適しています。
例:Amazon WorkSpaces、Microsoft Windows Virtual Desktop

02.クラウド構築のメリット
クラウド構築には多くのメリットがあります。ここでは代表的なものを紹介します。
コスト削減
クラウドサービスは初期投資を抑え、利用した分だけ課金される従量課金制を採用しているため、不要なリソースに対する支出を削減できます。オンプレミス環境に必要な設備費や維持費と比較して、経済的です。
運用・保守の負担軽減
クラウドベンダーがハードウェアやインフラの保守を行うため、ユーザー側の管理負担が軽減されます。これにより、本来の業務や開発にリソースを集中できます。
拡張性の確保
需要に応じて簡単にリソースを増減できるため、予測が難しいビジネスでも柔軟に対応できます。このスケーラビリティにより、新しい市場やプロジェクトへの迅速な対応が可能です。

03.クラウド構築の手順
クラウド構築を成功させるには、明確な計画と段階的な実施が不可欠です。以下に一般的なステップを解説します。
STEP①目的と要件の明確化
まず、クラウドを導入する目的を定め、業務要件を整理します。目的例として、コスト削減、業務効率化、スケーラビリティの向上が挙げられます。
業務要件には、システムが必要とする処理能力や応答時間、データの暗号化やアクセス制御、業界特有の規制やコンプライアンス要件(例:GDPR、HIPAA)、システムの稼働率やダウンタイムの許容範囲などが含まれます。
STEP②クラウドサービスの選定
次に、利用するクラウドサービスを選択します。ベンダーごとのサービス内容や料金体系を比較し、自社のニーズに合致するものを選びます。
評価基準としては、サービスの信頼性、提供されるサポートの種類や対応時間、セキュリティ機能、コストパフォーマンスなどがあります。
STEP③環境設計と構築
選定したクラウドサービス上で、必要なリソースを設計・構築します。
この際、ネットワーク設計やデータの保存方法、データベースの種類と設定、IAM(Identity and Access Management)や暗号化、ファイアウォール設定などのセキュリティ設定、そして定期的なバックアップのスケジュール設定とリストア手順の確立を行います。
STEP④移行とテスト
既存のデータやシステムをクラウドへ移行し、適切に動作するかテストを行います。移行計画を事前に詳細に策定し、段階的に移行を実施します。
データのエクスポート・インポート、データ整合性の確認、アプリケーションの移行と設定変更、機能テスト、パフォーマンステスト、セキュリティテストの実施を行い、テスト中に発見された問題の修正と再テストを行います。
STEP⑤運用開始と監視体制の整備
運用を開始し、継続的な監視体制を整備します。クラウドサービスプロバイダーが提供するモニタリングサービス(例:AWS CloudWatch、Azure Monitor、Google Cloud Monitoring)を活用し、異常が発生した際に通知を受け取るためのアラート設定を行います。
システムのパフォーマンスを監視し、必要に応じてリソースを調整し、セキュリティログの監視と異常検知を行います。リソースの利用状況やコストのレビューを定期的に実施し、最適化を図ります。
また、障害発生時の対応手順を策定し、定期的に訓練を実施します。

04.クラウドシステム運用におけるアウトソーシングの活用
クラウドのシステム運用の一部または全部をアウトソーシングすることも選択肢の一つです。アウトソーシングを活用することで、クラウド運用の専門家による高品質なサービスを受けることができ、自社内での運用負担を軽減し、コア業務に集中できるというメリットがあります。また、運用コストを予測しやすくなり、効率的なリソース管理が可能です。
具体的には、システムの監視とアラート対応を専門のサービスプロバイダーに委託したり、セキュリティ監視や脅威インテリジェンスの提供を専門業者に依頼したりすることが考えられます。データのバックアップ管理と災害復旧計画の策定・実施、システムのパフォーマンス最適化を専門家に任せることも有効です。
アウトソーシングを検討する際には、提供されるサービスの品質や対応時間を明確にするためのサービスレベルアグリーメント(SLA)やサービスレベルオブジェクティブ(SLO)の確認、外部業者が適切なセキュリティ対策と法規制への準拠を行っているかの確認、そしてアウトソーシングのコストが自社運用と比較してどの程度効果的かを評価することが重要です。

05.クラウド構築の注意点
クラウド構築にはいくつかの重要な注意点があります。これらを考慮して進めることで、トラブルを回避し、安定したクラウド環境を実現できます。
セキュリティ対策
クラウド環境においてセキュリティは最も重要な要素の一つです。まず、データの暗号化を徹底することが求められます。データの保存時(静止データ)および転送時(移動データ)の両方で暗号化を行うことで、データの安全性を確保します。クラウドプロバイダーが提供する暗号化サービス(例:AWS KMS、Azure Key Vault、Google Cloud KMS)を活用するのが一般的です。
次に、アクセス権限の設定を適切に行うことが重要です。最小権限の原則に基づき、ユーザーやサービスに対するアクセス権限を最小限に抑えます。これには、IAM(Identity and Access Management)を使用して、詳細なアクセス制御を設定することが含まれます。また、ネットワークレベルでのアクセス制御を強化するために、セキュリティグループやファイアウォールルールを設定することも必要です。
さらに、クラウド環境のセキュリティ設定やログを定期的に監査し、脆弱性や不正アクセスの兆候を検出する定期的なセキュリティ監査も欠かせません。
コスト管理
クラウドサービスは従量課金制であるため、無駄なリソース利用を防ぐためのコスト管理が重要です。定期的に利用状況を確認し、コスト管理ツール(例:AWS Cost Explorer、Azure Cost Management、Google Cloud Billing)を使用してリソースの使用状況を把握します。自動スケーリングの設定を行い、需要に応じてリソースを自動的に増減させることで、無駄なリソース使用を防ぎます。
また、リソースにタグを付けて、部門やプロジェクトごとにコストを追跡しやすくすることも有効です。予算を設定し、コストが一定の閾値を超えた場合にアラートを受け取るようにすることで、予算管理を徹底することができます。
障害対応計画
クラウド環境においても障害は発生する可能性があるため、事前に復旧計画を策定しておくことが重要です。災害発生時の復旧手順を詳細に策定し、定期的に訓練を行います。クラウドプロバイダーの災害復旧サービス(例:AWS Disaster Recovery、Azure Site Recovery、Google Cloud Disaster Recovery)を活用することで、迅速な復旧が可能となります。
データの定期的なバックアップを行い、バックアップデータの整合性を確認することも重要です。重要なシステムやデータを複数のリージョンやアベイラビリティゾーンに分散して配置し、冗長化を図ります。さらに、障害発生時に自動的に代替リソースに切り替えるフェイルオーバーの設定を行うことで、システムの可用性を確保します。
ベンダーロックインのリスク
特定のクラウドプロバイダーに依存しすぎると、将来的な移行が困難になるリスクがあります。このリスクを避けるために、複数のクラウドプロバイダーを利用するマルチクラウド戦略を採用することが有効です。例えば、AWSとAzureを併用するなどの戦略を検討します。
また、ベンダーに依存しないオープンスタンダード(例:Kubernetes、Terraform)を活用することで、クラウド環境の移行性を高めることができます。データを容易に移行できるように、クラウドプロバイダーが提供するエクスポート・インポート機能を活用することも重要です。
最後に、クラウドプロバイダーとの契約内容を確認し、解約時の手続きやデータの取り扱いについて明確にしておくことが必要です。これにより、将来的な移行がスムーズに行えるようになります。
06.まとめ
クラウド構築は、企業のIT戦略において重要な選択肢で、コスト削減や業務効率化といった多くのメリットを享受できます。
当社では、お客さまのご要件に応じた新規のクラウド基盤構築や、オンプレミスで運用しているお客さまの基盤のクラウド移行など、多数の実績があり、高品質の「AWS導入支援サービス」をご提供します。
また、当社が強みを持つシステム運用というゴールを見据えた設計・構築も特長です。これにより、運用フェーズでのコスト削減につながり、お客さまのビジネス成長に貢献することができます。
AWS導入支援サービスの特長
- 長年培った運用ノウハウを活かし、ゴールから設計図を引くことで、最適な環境を企画、ご提案します。
- 企画から運用まで、一気通貫したトータルなITサービスのご提供で、お客さまのIT戦略を長期的にサポートが可能です。
- お客さまのシステム課題を洗い出し、多彩なIT製品群からご提案のうえ、最適なシステム基盤を構築します。