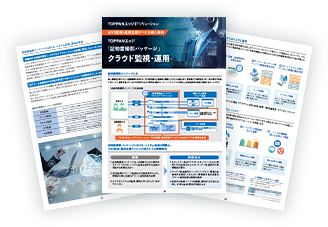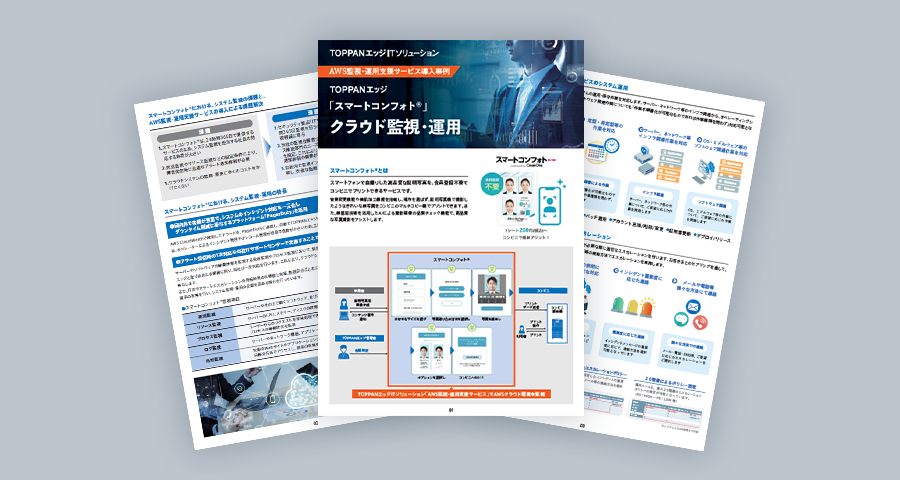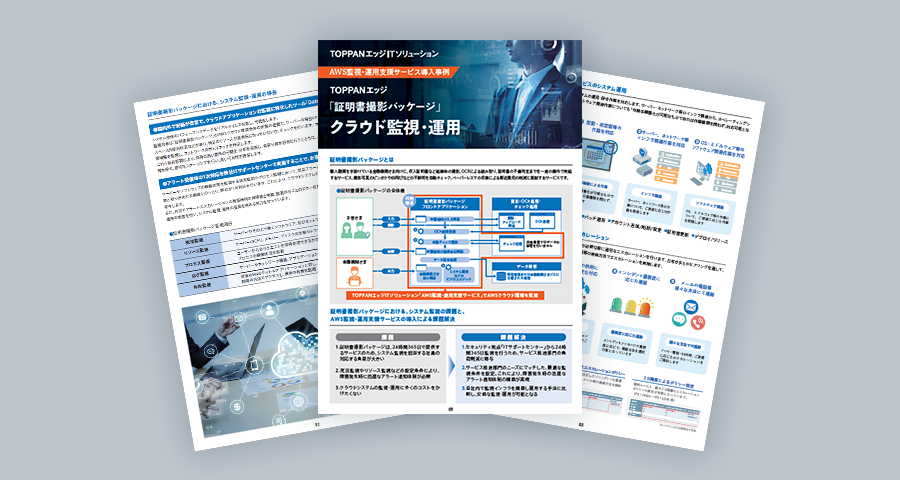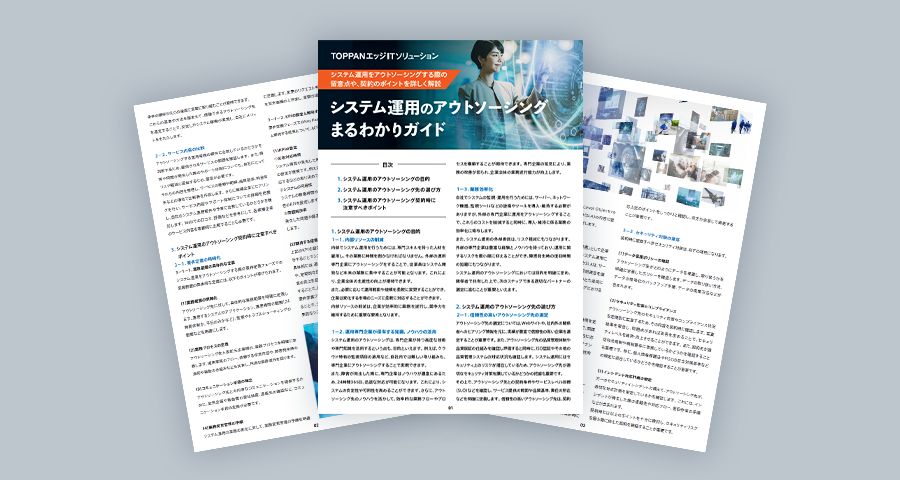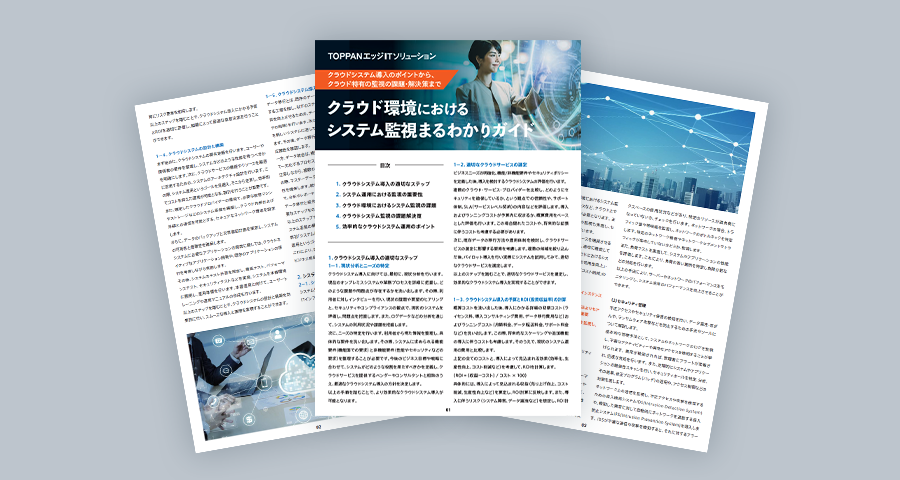システム運用保守とは?業務内容・違いについて解説

現代のビジネス環境では多くのシステムが使用されており、我々の生活の重要な基盤となっています。仮にそのシステムが何らかの原因で停止してしまうと、利用者に大きな影響を及ぼすため、システムが問題なく稼働するために行う「運用保守」が求められます。
今回は、そんなシステム運用保守を取り上げ、業務内容や実行にあたっての内製・外注についても解説します。
目次
閉じる
01.システム運用保守とは
システム運用保守とは、企業が業務システムやユーザー向けのSaaSサービスなどのシステムを、効率的かつ安定して運用することを指します。具体的には、システムの監視、トラブルシューティング、パフォーマンスチューニング、セキュリティ対策などが含まれます。システム運用オペレーターや運用管理者は、定期的なソフトウェアやハードウェアのメンテナンス、セキュリティパッチの適用などのアップデートを行うなど、システムが正常に稼働し続けるために必要な作業を行い、システムの安定性や可用性を確保する役割を果たしています。障害発生時には手順書に沿った作業を行い、不具合の原因究明と復旧を行います。これにより、企業は効率的に業務を運営し、顧客に対して高品質なサービスを提供することが可能になります。
02.システム運用保守における「運用」「保守」の違い
システム運用保守における「運用」と「保守」は、関連性があるものの、それぞれ異なる役割と目的を持っています。以下にその違いを詳しく解説します。
システム運用
システム運用は、情報システムが日常的に正常に機能するように管理・監視する活動を指します。例えば、システムのパフォーマンスや稼働状況のリアルタイムの監視、データ損失に備えた、定期的データのバックアップ、システム利用者からの問い合わせやトラブルに対するユーザーサポート、システムのセキュリティを維持するための管理、システムのパッチ適用やアップデートの実施が挙げられます。
システム保守
システム保守は、システムの機能や性能を維持・改善するためのメンテナンス活動を指します。具体的にはシステムに存在する不具合やバグを修正する作業、ユーザーのニーズに応じた新しい機能の追加や、不具合を改善したプログラムやシステムの導入、システムに関するドキュメント類を最新の状態に保つ管理といった業務が挙げられます。
まとめると、システム運用は日常的な管理や監視を中心とし、システム保守は機能の維持や改善に焦点を当てています。両者は相互に関連しており、システムが円滑に運用されるためには両方の活動が欠かせません。

03.システム運用保守の業務内容
システム運用保守の業務内容は多岐にわたり、主に以下のカテゴリーに分類されます。それぞれの業務内容について詳しく説明します。
(1)日常運用業務
システムの稼働状況やパフォーマンスをリアルタイムで監視するため、Zabbix、Datadogなどの監視ツールを使用し、異常が発生した場合にアラートを受け取り、迅速に関係者への報知や、原因の特定、障害復旧に当たります。
(2)メンテナンス
ハードウェアやソフトウェアの定期的な点検・保守を行います。OSやソフトウェアの脆弱性を修正するセキュリティパッチの適用や、プログラムのアップデートを実施し、定期的なセキュリティ監査によるシステムの安全性を保持します。
(3)バックアップとリカバリ
定期的にデータのバックアップを行い、データ損失に備えます。バックアップからの復旧手順をテストし、実際に障害や問題が発生した際に迅速に対応し、ユーザーの機会損失を最小限に抑えます。
(4)ユーザーサポート
ユーザーからの問い合わせやトラブルシューティングに対応します。ユーザーアカウントの作成、変更、削除などのユーザーアカウントのアクセス制限の管理を行い、不正アクセスを防止します。
(5)パフォーマンス管理
CPU、メモリ、ストレージなどのリソース使用状況を監視し、ボトルネックを特定、システムのパフォーマンスを最適化するための設定変更やリソースの再配分を行います。また、システム変更した場合、そのリスクや影響を分析します。
(6)セキュリティ管理
システムへのアクセス権限を適切に設定し、ユーザーの認証と承認を行います。また、システムのセキュリティリスクを評価し、脆弱性を特定します。必要に応じて改善措置を講じます。
(7)ドキュメント管理
システム運用に関する手順書やマニュアルを作成・更新します。また、システムの変更履歴やトラブルシューティングの記録を管理します。
(8)災害復旧計画策定
災害発生時の復旧手順や役割分担を定めた計画を策定します。復旧の訓練やシミュレーションを定期的に実施し、万一、災害が発生した場合に備えて、日頃より不測の事態への対応力を高めます。
このように、システム運用保守の業務は多岐にわたりますが、全ての活動がシステムの安定運用と長期的な信頼性を確保するために重要です。また、業務を効率的に進めるためには、チーム内でのコミュニケーションや情報共有も不可欠です。

04.システム運用保守の内製と外注について
システム運用保守の内製化の利点と留意点
システム運用保守を内製(自社で実施)するケースには、いくつかの利点や目的がありますが、同時に留意しなければならない点もあります。以下に詳しく解説します。
<内製の利点>
社内でシステム運用保守をすることで、システムに関する専門知識やノウハウが社内に蓄積され、運用保守人員のスキル向上にもつながります。これにより、障害発生時などでの問題解決の迅速化が図れます。
また、社内の運用チームは、自社のサービスや業務プロセスに精通しているため、システムの運用保守がビジネスニーズに合った形で行い易いというメリットもあります。
<留意すべき点>
内製を行うためには、専門的な知識や技術を持った人材が必要です。これらの人材が不足している場合、育成や採用に時間とコストがかかります。新しい技術やシステムに対応するためのトレーニングも必要となり、教育プログラムを整備し、チームのスキル向上を図る必要があります。また、運用作業が標準化されていないと、運用保守の属人化の懸念とともに、作業の品質が確保できないなどのリスクがあるため、運用手順やマニュアルの整備が重要です。
さらに、社内の人的リソースや時間的リソースが限られている場合、運用保守業務が他の業務に影響を及ぼす可能性があります。新サービス立ち上げの場合、そのサービスの開発担当者がそのまま運用保守業務まで携わっているケースがあり、特に、運用業務の繁忙期には本来の開発業務への影響が懸念されます。
<内製に関するまとめ>
システム運用保守を内製することには、多くの利点がありますが、その実行には注意が必要です。特にリソースやスキルの確保、標準化、教育、継続的改善に対する取り組みが欠かせません。これらを適切に管理することで、内製の効果を最大限に引き出すことが可能です。
システム運用保守の外注の利点と留意点
システム運用保守を外注する場合、多くの利点がありますが、同時に考慮すべき留意点も存在します。以下に、外注の利点や、留意すべき点を詳しく解説します。
<外注の利点>
自社の人的リソースや時間的リソースが限られている場合、外部の専門企業に委託することで、運用保守業務を安定的に行えるようになります。また、自社でシステムの監視・運用を行うためには、サーバー、ネットワーク機器、監視ツールなどの設備やツールを導入・維持する必要がありますが、外部に運用保守をアウトソーシングすることで、これらのコストを削減すると同時に、導入・維持に係る業務の効率化に寄与します。
さらに、特定の技術や知識が必要なシステムの場合、外部の専門企業に委託することで、高い専門性を得られます。例えばクラウドサービスの運用保守では、APM(Application Performance Monitoring)に対応している専門企業に委託することで、多くのメリットを享受できます。APMを活用した監視により、アプリケーションやコードに潜むパフォーマンスの問題を即座に特定して対処する事ができます。APMでは、アプリケーションの内部動作やコンポーネント間の相互作用をモニタリングし、パフォーマンスをリアルタイムで可視化します。遅延や障害があった場合、そのボトルネックやリソースの過負荷など、問題の根本原因を特定、情報を収集し、対処を可能にします。クラウド環境ではアプリケーションのスケーラビリティが重要となるため、APMは、アプリケーションの負荷状況を監視、スケーリングの必要性を判断するための情報を提供します。適切なスケーリング戦略を実践することで、アプリケーションのパフォーマンスと可用性を確保することができます。障害発生時も、外部の専門企業の高い知見により、迅速な復旧が行えるなど、リスク管理の観点でもメリットがあります。
<留意すべき点>
専門企業とは、サービスレベルアグリーメント(SLA)や業務範囲を明確に定める必要があります。合意内容が不明確だと、期待通りのサービスが得られないリスクがあります。また、専門企業との定期的なミーティングで運用実績のフィードバックを行うなど、コミュニケーションの確保が重要です。あらかじめ評価基準を設定した上で、システム運用保守専門企業のサービス品質を評価し、必要に応じて改善を求めます。その企業の契約期間や費用、サービスの内容が将来的にも適切であるかを評価し、市場の変化や自社の成長に応じて、継続的に見直しを行っていきます。
<外注に関するまとめ>
システム運用保守を外注することで、専門的な技術の導入やリソースの効率的な活用が可能になりますが、コミュニケーションや契約内容、品質管理などに関する留意点もあるため、自社の目的に沿った適切な外部サービスを選定することが重要です。
当社「AWS監視・運用支援サービス」は、クラウド監視の分野で世界的に導入が進んでいるDatadogを標準装備し、APMによる監視など、クラウドに特化したモニタリングに特長があります。また、50年にわたるシステム運用実績に裏付けられた高品質の運用保守サービスの提供が可能です。
当社にクラウドシステムの監視・運用をアウトソーシングしていていただくことで、お客さまにとって、運用に必要なリソースの最適化に寄与するとともに、ビジネスの成長に貢献することができます。

AWS監視・運用支援サービスの特長
- 24時間365日、国内最高水準の高いセキュリティを誇るデータセンター拠点から監視・運用サービスを提供
- 50年にわたるシステム運用実績に裏付けられた、ITエンジニアとオペレータによる高品質のサービスを提供
- クラウドファーストの時代に対応。お客さまのニーズに応じた、最適な監視項目の提案など、高い柔軟性を有しています。

執筆者
TOPPANエッジITソリューション(株) コラム編集室
システム監視・運用、インフラ構築をはじめとした、IT専門企業のTOPPANエッジITソリューションでは、主にシステム運用、基盤構築に関するコラムを発信し、企業にお役立ていただきます。システムのクラウド化、運用のアウトソーシングなどの、ビジネスシーンで活用していいただければ幸いです。