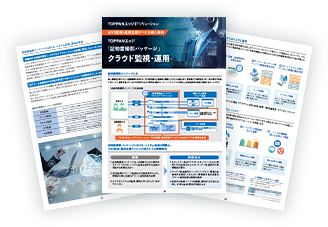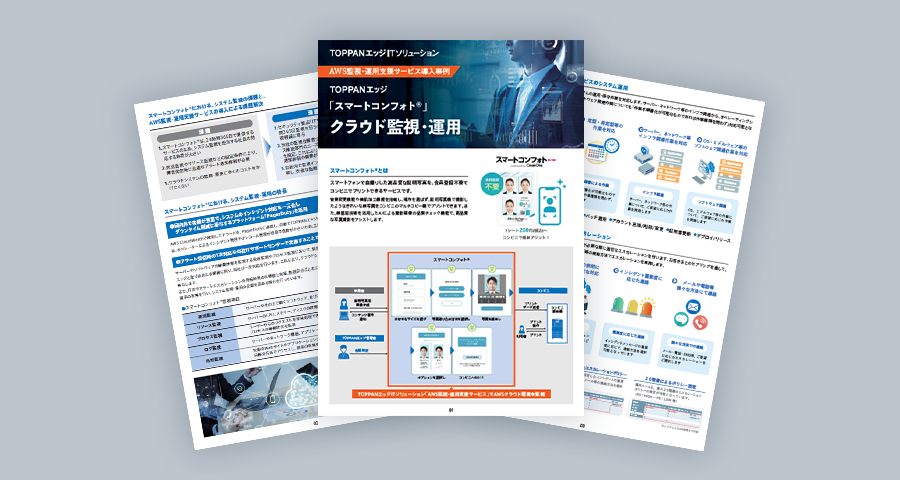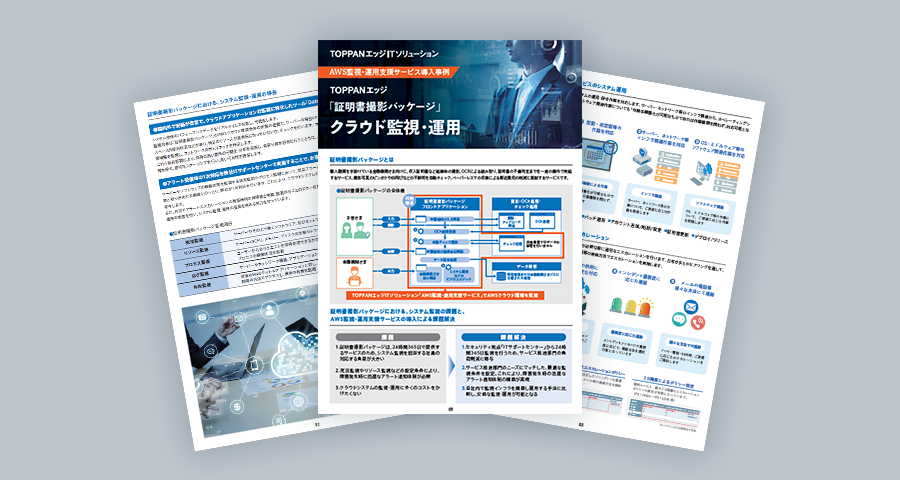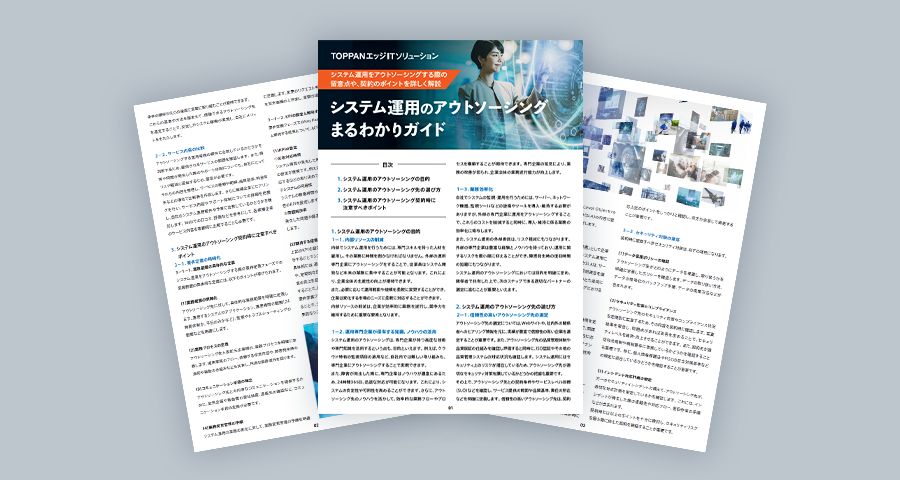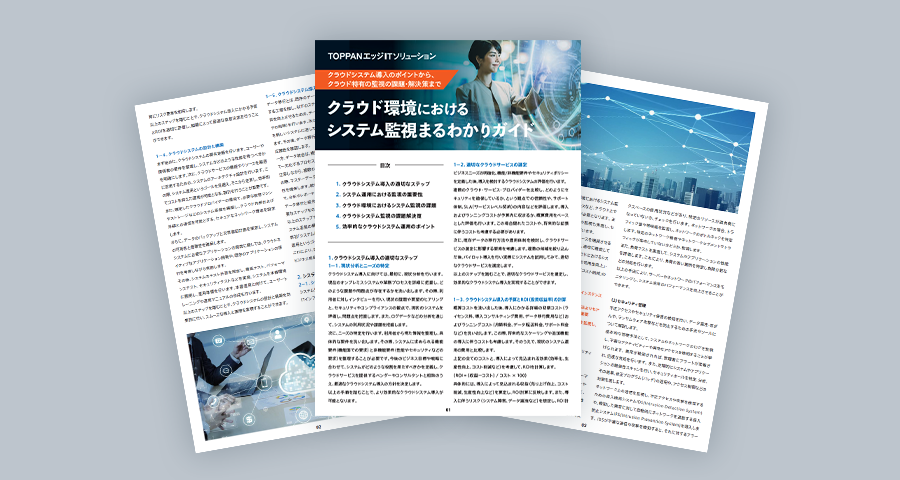システム運用の実績から学ぶ企業の成功戦略とは?成功事例もご紹介

システム運用とは、企業が業務システムやユーザー向けのSaaSサービスなどのシステムを効率的かつ安定して運用することを指します。 本コラムでは、システム運用の実績から成功させるための戦略やポイントを解説します。成功事例もご紹介いたします。
目次
閉じる
01.システム運用とは?
システム運用とは、企業が業務システムやユーザー向けのSaaSサービスなどのシステムを、効率的かつ安定して運用することを指します。 具体的には、システムの監視、トラブルシューティング、パフォーマンスチューニング、セキュリティ対策などが含まれます。
システム運用オペレータや運用管理者は、システムが正常に稼働し続けるために必要な作業を行い、システムの安定性や可用性を確保する役割を果たしています。 また、定期的なメンテナンスやアップデートなども含まれるため、システムの運用状況を常に把握し、適切な対応・サポートを行うことが重要です。
02.企業におけるシステム運用の役割
企業におけるシステム運用の役割は、いくつか挙げられますが、まずシステムの監視と障害発生時のトラブルシューティングが大きな要素を占めます。 システムの稼働状況やパフォーマンスを監視し、問題が発生した際、迅速に対応しトラブルを解決します。 継続的に、サーバやネットワーク機器などのシステムアップデートを行い、ソフトウェアへのセキュリティパッチの適用など、システム保守にも取り組みます。 システム監視と保守の技術高め、品質を向上させる事は、障害発生時の復旧時間の短縮につながり、企業の経営効率化にも寄与します。
さらに、システムの運用データを分析し、効率的な運用方法やシステムの改善点を見つけ出し、常にシステムの安定性を向上させる活動も重要なポイントです。

03.システム運用の成功要因
システム運用を成功させるためには、まず、システム導入前に綿密な計画と戦略を策定することが重要です。運用の目標や方針、役割分担、リスク管理などを明確にします。 その上で、システム運用に精通した適切な人材配置や、システム監視ツール、アラートの自動発報ツールなどを導入することで、効率的な運用が可能となります。
システム運用の過程において適切な変更管理も必要です。運用稼働後に、課題や改善点を発見、運用手順等の変更がシステムに与える影響を正確に把握し、適切に管理者の承認を経て変更を実施することで、システムの安定性を保つことができます。
また、過去のシステム運用実績を活用することも重要なポイントです。全く同一のシステム導入ではなくとも、過去のシステム運用実績から傾向と対策を立てることができます。
これらを遂行することによりシステム運用を成功に導くことができます。
04.システム運用実績を活用した企業の成功戦略
システム運用実績の活用は、企業経営を成功に導くための重要な要素となります。以下に、いくつかのポイントを挙げて、成功に向けた戦略を解説します。
ユーザー満足度の向上
過去のシステム運用実績を分析することで、ユーザーからの苦情や問題がどのようなパターンで発生しているかを把握します。
この情報の活用によって、問題の再発防止策を講じると同時に、ユーザーがどんな点で満足しているか、不満を抱えているかを把握し、サービス向上のための改善策を講じることができます。
また、運用実績の分析は、効率的なカスタマーサポートの観点でも有効です。ユーザーが同じ問題について繰り返し問い合わせることがないよう、適切な情報提供を行うことができます。
さらに、過去の実績を踏まえた、システムの信頼性向上や障害予防措置を行うことで、ユーザーの信頼を獲得し続けることができ、ユーザー満足度の向上につながると言えます。
コスト削減とROIの向上
過去のシステム運用実績を分析することで、リソース(人員、機器、ソフトウェアなど)の使用状況やシステムの負荷を把握します。余剰なリソースの削減とリソースの適切な配置により、コストを削減することが可能となります。
また、運用実績情報を基に、問題が発生した際の対応ノウハウを蓄積し、障害時に迅速に対応することで、システムの信頼性を高めると同時に、労務コストを削減することができます。
さらに、投資したシステムの費用対効果の評価や、適切なシステム運用の指標の分析は、投資収益率(ROI)の向上につながり、経営視点での財務状況の健全化にもつながります。
競争優位性の確保
システム運用実績を活用することで、企業は競争優位性を確保するための戦略を構築することができます。
市場のトレンドや競合他社の動向を分析し、革新的なサービスや機能の提供に取り組むことが重要となります。
これにより、競合他社との差別化を図り、競争優位性を築くことができます。
また、リスク要因や障害の発生パターンを把握することで、リスク管理策を強化し、システムの安定性を確保します。
システムの安定性が高いと市場で認知されている企業は、新しいサービスを市場に提供する際も、顧客からの支持を得やすくなります。
さらに、過去のシステム運用実績を通じて得られた知見を活用し、従業員の能力向上に取り組むこともできます。
これにより、競合に比較し優秀なエンジニアを育成し、企業の競争力を強化することができます。
これらのポイントを踏まえて、過去のシステム運用実績の活用により、顧客満足度の向上、ROIの向上、競争優位性を確保し、企業の持続的な成長を実現します。

05.システム運用実績を活用して成功した企業の実例
システム運用の成功事例を、以下2社を例に解説します。
NTTデータフォースのシステム運用成功の要因
2000年より大手地方銀行のシステムを受託し、企画・提案から基盤構築、開発、運用保守まで手掛けるNTTデータフォースでは、徹底した品質管理システム(QMS)に基づくシステム運用を実施しています。 その中で、運用に関する独自の社内制度を設けています。 これは、運用の本来の在り方をベースにしながら、拠点ごとの制約事項も踏まえて、各センターごとに最適な運用手法を分析、評価し、制度として確立したものです。 また、継続的にその制度の課題を発見し改善する、という活動も行っています。同社では、自社の社員以外に、他企業からオペレータやエンジニアが常駐していますが、それら企業に全てを任せることなく、自社で意思を持ってルールを定義し、より良いものに改善する、という活動が、高品質のシステム運用を実現できている成功要因と言えます。
キンドリルジャパンのシステム運用実績から学ぶ成功のポイント
ITインフラのコンサルティング、構築、運用、保守を手掛けるキンドリルジャパンでは、大手金融機関のTSUBASA共同システムなどの、ミッションクリティカルなシステム運用を行っています。 TSUBASA共同システムでは、全国複数の拠点でシステム運用を行っており、1拠点に依らず、全国の拠点で均しく安定稼働を実現し、高品質な運用サービスを金融機関に提供する必要があります。 そのため、エラーを最小化する取組みやプログラムなどを1拠点で発案・実行した際、タイムリーに各拠点に共有する仕組みを構築し、実践しています。 これにより、システム運用においてノーミスの継続500日を達成するなどの成果を上げています。このような、拠点間コミュニケーションを重視した堅実な取組みが、成功につながっていると言えます。
06.システム運用の今後の展望
システム運用市場では、クラウド移行の潮流が加速すると言えます。企業はクラウドを活用することで、インフラの運用負荷を軽減し、スケーラビリティや可用性を向上させることができ、リモートワークによる働き方改革や、グローバル展開によるビジネスのスケール化を実現することができます。
また、技術革新により、自動化技術やAIを活用した運用ツールの導入が進み、NoOps(No Uncomfortable Opsの略。「システム運用の嬉しくない事を無くす」を目指すための技術やアーキテクチャ、それを実現するための活動)が進展すると言えます。
将来、これらの潮流により、システム運用は、より効率的で効果的なものとなるでしょう。企業はこれらのトレンドに積極的に対応し、最新の技術やサービスを取り入れることで、競争力を維持し成長していくことができます。
当社「AWS監視・運用支援サービス」は、クラウドに特化した監視項目が特長で、お客さまのクラウド環境を監視・運用します。また、市場の潮流をいち早く捉え、最新の自動モニタリングや、アラートの自動発報機能を装備し、効率的なシステム運用を実現し、お客さまのクラウドシステム運用のさまざまな課題を解決します。
AWS監視・運用支援サービスの特長
- 24時間365日、国内最高水準の高いセキュリティを誇るデータセンター拠点から監視・運用サービスを提供
- 50年にわたるシステム運用実績に裏付けられた、ITエンジニアとオペレータによる高品質のサービスを提供
- クラウドファーストの時代に対応。お客さまのニーズに応じた、最適な監視項目の提案など、高い柔軟性を有しています。

執筆者
TOPPANエッジITソリューション(株) コラム編集室
システム監視・運用、インフラ構築をはじめとした、IT専門企業のTOPPANエッジITソリューションでは、主にシステム運用、基盤構築に関するコラムを発信し、企業にお役立ていただきます。システムのクラウド化、運用のアウトソーシングなどの、ビジネスシーンで活用していいただければ幸いです。